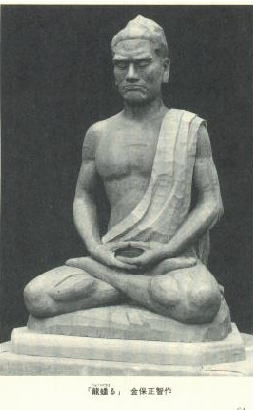 仏陀は「苦」の克服をめざして出家されたといわれますが、その「苦」(dukkha)とは、中村元博士によると「自己の欲するままにならぬこと」をいうとされます。何が自己の欲するままにならないのかというと、それは自己が注意を向けている対象でしょう。
仏陀は「苦」の克服をめざして出家されたといわれますが、その「苦」(dukkha)とは、中村元博士によると「自己の欲するままにならぬこと」をいうとされます。何が自己の欲するままにならないのかというと、それは自己が注意を向けている対象でしょう。そこで、「自己の欲するままにならぬこと(苦)」を克服する方法として、対象を自己の欲する方向に変えていくということが考えられます。これが自然科学のやり方ですし、私たちの常識となっている考え方でもありましょう。
この場合の苦の原因は対象にあることになりますが、仏陀は苦の原因を対象には求めず、妄執(渇愛)、即ち私たちの心の側に求め、妄執(渇愛)をなくせば、苦もなくなり、それが涅槃、即ち悟りであると説かれました。そして涅槃(悟り)に到る方法(道)も細かく説いておられます。
しかし、なぜ仏陀は苦の原因を対象に求めなかったのでしょうか。それは対象が「無常」(勝手に変化するもの)であり、元々こちらの思うままにならないものであることを見破られたからでしょう。
道元禅師は悟りを「身心脱落」という言葉で表現しておられます。それをまた「自己をわするる」こと、あるいは「万法に証せらるる」こととも述べておられます。これを高崎直道博士は「対象たる万法にすべてをあずけてしまう」ことであり、「万法の内に入り込んで、それになりきること」であると解説されています(『仏教の思想11古仏のまねび〈道元〉』角川書店)。
この解説に従って、「自己」に「心」を、「万法」(対象)に「身」を当てはめますと、「心をわすれて身になりきる」となります。これは 「身心一如」ということであり、これが「身心脱落」の意味だということになりましょう。
そして「身心脱落」に到る手段は「只管打坐」(わき目もふらずにただ坐禅をすること)とされますから、「心をわすれて身になりきる」坐禅をすればよいということになりそうです。「身になりきる」とは、生老病死(無常)を経過する自分の身体に文句を言わず、そのまま受け容れることかと思います。(平成12年6月)