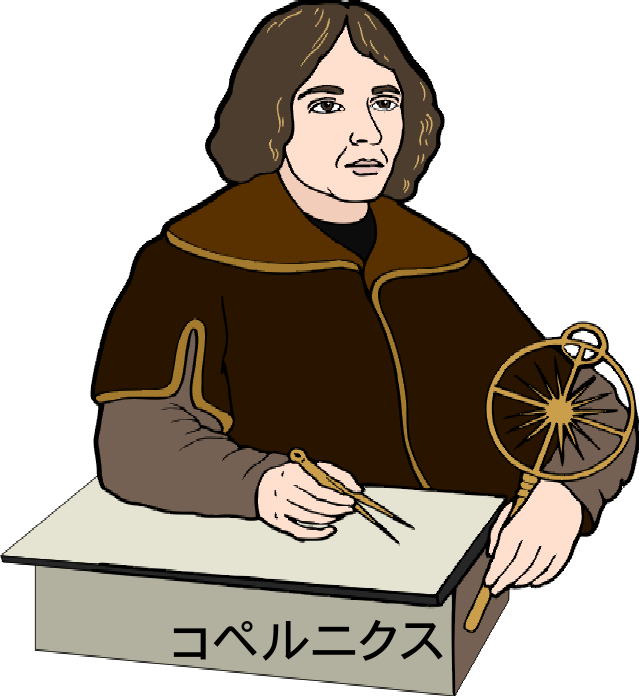 東海村にある核燃料加工施設で臨界事故という信じられない事故が発生しました。原子力に対する不信感が広がっています。しかし現代社会は科学技術の恩恵の上に成り立っています。簡単には行きません。そこで、恩恵にあずかっている科学技術あるいは自然科学というものはいったい何であるか、少し掘り下げて考えてみたいと思います。
東海村にある核燃料加工施設で臨界事故という信じられない事故が発生しました。原子力に対する不信感が広がっています。しかし現代社会は科学技術の恩恵の上に成り立っています。簡単には行きません。そこで、恩恵にあずかっている科学技術あるいは自然科学というものはいったい何であるか、少し掘り下げて考えてみたいと思います。科学史の専門家である村上陽一郎さんは、自然科学というものはユダヤ・キリスト教の伝統の中で生まれたもので、近代科学の父と呼ばれるコペルニクスやガリレオ、ニュートンなどは、実は神学をやっていたのとだ指摘されています。
旧約聖書の創世記に、神が世界を造る際に、人間を神に似せて造り、人間以外の自然は人間が支配する人間のすみかとして造ったとあります。すなわち、世界(人間と自然)は神によって「造られた」ものなのです。
「造られた」ものであれば、その中に造ったものの意志や計画が秘められていると考えられます。ですから、スコラ哲学の言葉に「神は二つの書物を書いた。一つは聖書であり、もう一つは自然という作品である」とあるそうです。
この自然という書物を一ページづつ読んで神の意志を知ろうしたのが、コペルニクスたちだから、それは神学だったのだというのです。例えばコペルニクスは天動説を否定して地動説を唱えましたが、彼の問題意識は、宇宙の中心は太陽か地球かということでした。伝統的考えでは地球が中心だったのですが、彼は太陽だと考えました。その理由は、神が世界を造るとき、神が「光あれ」と言いうと、光があり、昼と夜が分かれ、これが第一日である、と聖書にあるのに基づき、この「光」を太陽であると考えたからです。
太陽が宇宙の中心であれば、おのずと地動説が導かれます。確かに神学と言うべきでしょう。そして、同じ聖書の「自然は人間が支配するものとして造られた」という言葉には、自然科学の本質が隠されているように思います。(平成11年11月)